武田鉄矢さんのラジオ「三枚おろし」で紹介されていた本に「腸と脳──体内の会話はいかにあなたの気分や選択や健康を左右するか」というタイトルがあった。
悩みで胃が痛む。大事なプレゼンの前にトイレに行きたくなる。どうにも「腑に落ちない」。
誰しも一度は経験があるこれらの感覚は、実は腸と脳が休むことなく交わしている「見えない会話」の表れだという。
言われてみれば納得がいく。
「ムカつく」というのも、頭で判断しているというよりは、まず内臓が反応している。腸や胃がざわめき、その感覚を脳が筋肉に伝えて顔をしかめたり声を荒げたりする。
私たちが思考していると思っていることの多くは、実は身体の奥からの声を翻訳したものに過ぎないのかもしれない。
この話を聞いて思い出したのが、三木茂夫の『内臓とこころ』という本だ。人間の心は脳ではなく、むしろ内臓に深く根ざしていると説いた名著である。
現代科学が「腸は第二の脳だ」と言い出したことを、三木はずっと以前に直観していたのではないかと思う。
以前、体重コントロールがうまくいかないという方と話したことがある。
「食べることで代償していることがあるのでは?」と問いかけても「わからない」と返ってくる。そこで「じゃあ、無意識ちゃんに聞いてみましょう」と促したら、ふいに「怒りです」と答えが出てきた。
「ほら、ちゃんとわかっているじゃない」と言うと、「今、閃きました」と本人も驚いた様子だった。
「では、その怒りを別の方法で表せないか」とさらに問いかけると、しばし沈黙。
そこで私の口から、なぜか「ワラ人形で怒りを静めましょう」と言葉が飛び出してしまった。
思わず相手は大声をあげて笑い出し、「それ、いいです!」と頷いた。
腸と脳の会話を思えば、この瞬間もまた内臓が発した声を、脳がユーモラスな形に翻訳しただけなのかもしれない。
怒りが「食べること」に化けるのではなく、「笑い」に変わったとき、身体の奥で何かがすっと解放されたように見えた。
今月は、改めて三木茂夫の『内臓とこころ』を読み返してみようと思う。
腸と脳、そしてこころ。
身体の深部で続いている「見えない会話」に耳を澄ませば、こころの奥にある静かな声も聞こえてくるかもしれない。
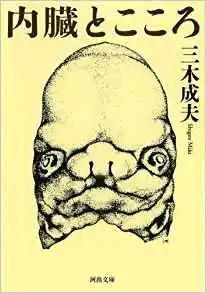
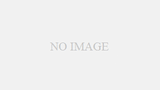
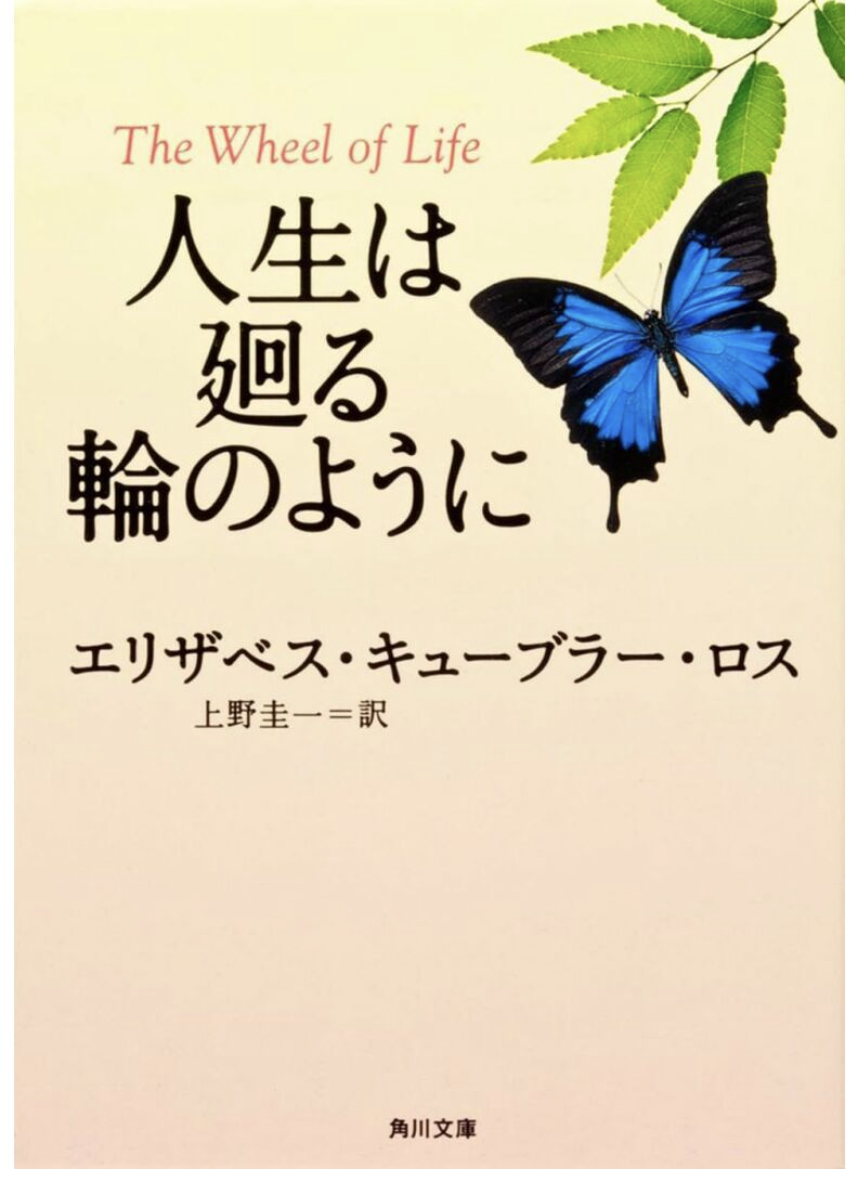
コメント