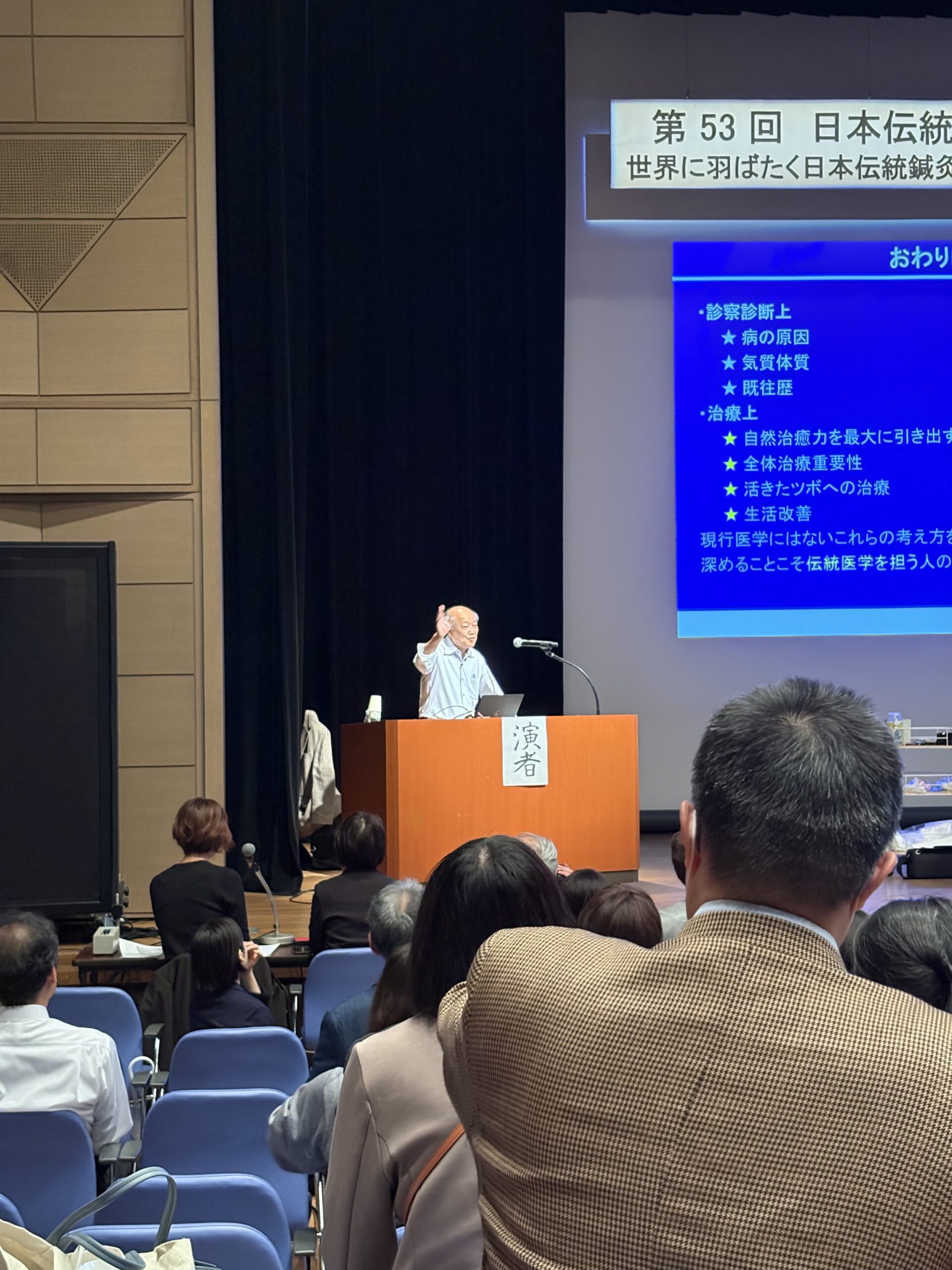10月11日に、スティーブン・バーチ(Stephen Birch)先生の特別講演を拝聴しました。私が特に関心を寄せているのは、「手の感覚をどう構築するか」です。触診では皮膚や筋肉の“名前”は同じでも、実際の触感は人によりまったく異なります。100人いれば100通り。初学の段階では傾向が見えにくく、一律の触り方や方法論で学び始めても、上手く進む人と行き詰まる人に分かれがちです。ここが学校教育では掘り下げづらい部分だと感じます。
バーチ先生は中国系の鍼灸も学ばれたとのことで、本当は講演後に質問したかったのですが時間が足りませんでした。懇親会でも先生はご挨拶に引っ張りだこ。ちょうど写真撮影の後、隣席になったご縁で声をかけ、通訳の方が不在だったところへ、たまたま形井秀一先生が来られたので、失礼を承知で通訳をお願いしました。
私は先生に「手の感覚は、どのくらいの期間で分かるようになりましたか」と尋ねました。その際、先生の前腕の皮膚を軽く触れさせていただいたのですが、「この皮膚と筋肉に同じように鍼を刺すのはあり得ない」と直感するほど質感が明確でした。皮膚・筋肉の“体質”の分け方が分からないと前に進みにくい。私自身、手の感覚を組み立てる過程で大いに苦労したため、期間をうかがったのですが、先生は「人によって違うのではないでしょうか」と穏やかに答えてくださいました。
バーチ先生は東洋はり医学会(Toyohari)の欧州代表を務められた方でもあります。鍼には九鍼という分類があり、体質や状況に応じて使い分ける考えがあります。手技も同じで、同一のやり方が常に奏効するわけではありません。その差を分ける鍵が、皮膚や筋肉の弾力、きめ、張りなどの触感です。
私の師である戸ヶ崎正男先生は、体質だけでなく「時間軸」によっても皮膚・筋肉の状態が変化することを明確に言語化し、四型分類として整理されました。これが分かると、施術部位の優先順位や予後の見通しが立ちやすくなります。
今回は短い時間で掘り下げ切れなかったのが心残りですが、またお会いできる機会を楽しみにしています。