徳富蘆花の随筆『みみずのたはごと』を手にして以来、暮らしている粕谷の風景がいっそう身近に感じられるようになった。
蘆花は都心を離れ、この粕谷村に移り住み「美的百姓」と称して畑を耕しながら、晴耕雨読の日々を綴った。近所の風景が描かれているだけに、今を生きる者として興味深く読める。
随筆の中には、当時の物乞いや不倫をユーモラスに描いたくだりもあり、思わず笑ってしまう。ある日ふらりと現れた「関」という翁の話は特に印象深い。渡り鳥のように北海道から東京へ越冬にやって来ては、八十代にして蘆花を陸別へと誘った。蘆花一家が汽車の開通翌日に陸別へ到着する描写を読むと、かつて自分が昭和三十年代に体験した北海道の原生林の面影が重なり、懐かしい思いに包まれた。
粕谷図書館に立ち寄れば、当然のように蘆花の著作が並んでいる。地元に根を下ろした文人が残したものの存在感を、あらためて実感する。
「ミューズの微笑み」と美術の発見
先日、深夜に偶然観たNHKの番組「ミューズの微笑み」では、写真家・植田正治が紹介されていた。正直それまで写真に強い興味はなかったのだが、彼の作品の詩心あふれる構図には心を打たれた。写真がこんなに豊かに語りかけてくるものだとは。
前回放送では北海道・十勝の「中札内美術村」が取り上げられていた。原始林を抜けて辿り着く美術館は、訪れる人に特別な体験を与えてくれる場所だという。旅先で立ち寄りたい場所がまたひとつ増えた。
白洲正子の武相荘と「お灸点」
次回の放送予告には、白洲正子の住まい「武相荘」の名があった。麻生区に住んでいた頃、歩いて行ける距離にありながら一度も訪ねなかったことを思い出す。あの周辺には神蔵家という旧家もあり、昭和四十年代までは「お灸点」と呼ばれて近隣の人々が灸を受けに集まっていたという。
その後は香具山美術館、現在の香山園美術館として資料館に姿を変え、灸道具なども展示されていたそうだ。何度か見学の連絡を試みたものの縁がなく、今も心残りのひとつである。
地名研究の方に伺った際には、「三輪や香具山といった奈良との縁を思わせる説は俗説にすぎない」と聞かされ、少し落胆した覚えがある。それでも白洲正子が惹かれた土地の響きや洒落心は、今も残っているように思う。
蘆花の随筆を通して地元の風景を重ね合わせ、北海道の記憶を呼び覚まされ、さらに美術や写真、白洲正子の住まいへと興味がつながっていく。暮らす土地を軸に歴史や芸術を読み解くことは、日常を豊かにしてくれるひとつの楽しみ方だと感じている。

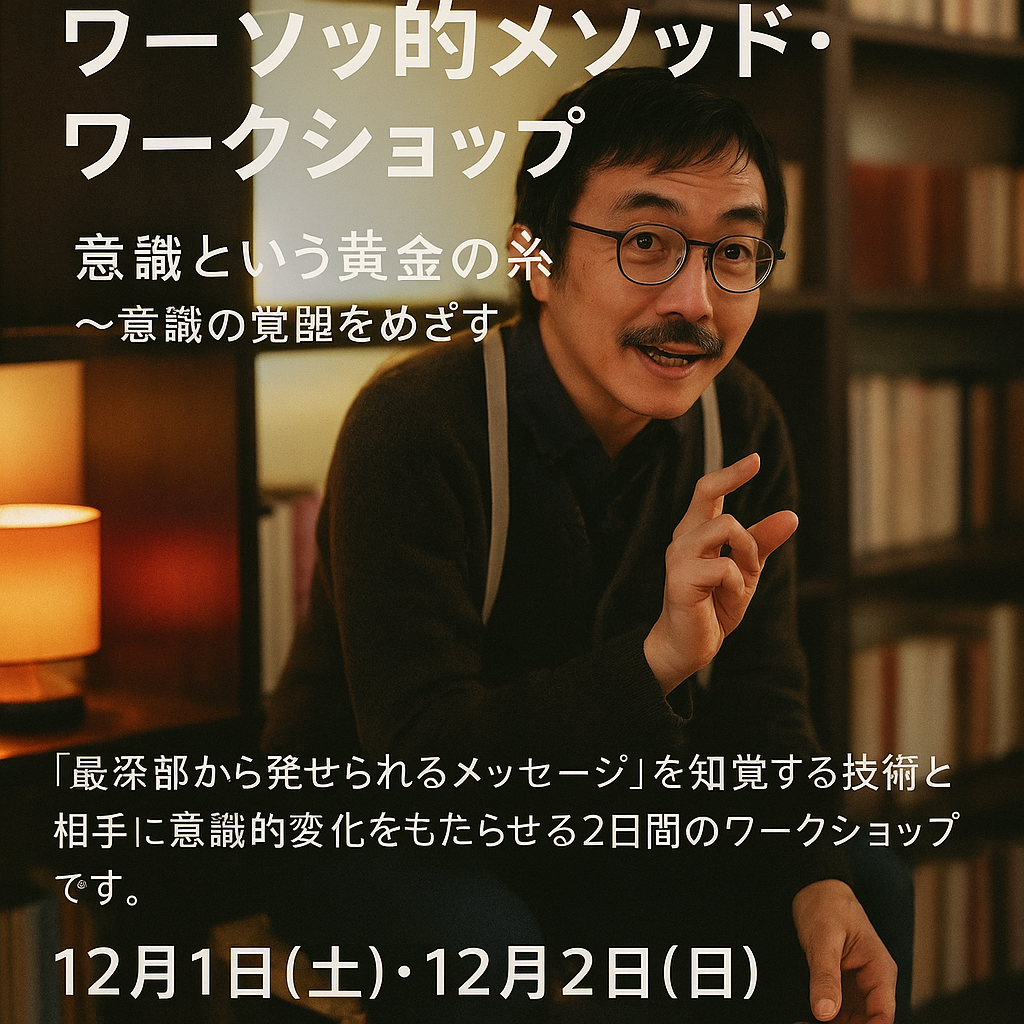

コメント