日本の小児はりは、すでに300年前の文献に記録が確認でき、大阪・河内地域で発生したと考えられています。
しかし成り立ちは一子相伝の形で受け継がれてきたため、詳細はほとんど分かっていません。一子相伝とは、その技術を跡継ぎの子供にしか伝えない方法。結果として多くの流派が途絶え、貴重な経験やデータが失われてしまったのは残念なことです。
現在では、小児はりは鍼灸師の間で再び注目を集め、活発に研究・実践されています。医療制度の整った日本では、たとえば東京都では中学生まで医療費が無料。こうした環境の中で、予防医学として小児はりをどう残していくかが課題になっています。
小児はりが発達した背景のひとつには、かつての高い乳幼児死亡率があると考えられます。明治・大正期、富国強兵や殖産興業の流れの中で、過酷な労働環境が女子や乳幼児の健康に影響した可能性があるのです。そのため、子どもの健康を守る予防医学として小児はりが着目されたのではないでしょうか。
「疳の虫」といえば夜泣きや癇癪のイメージが強いですが、もともとは症状を5つに分類した中の一つであり、夜泣きや癇癪だけを指すものではありません。
小児はりは、特殊な鍼を用いて皮膚を刺激する技術です。流派によって作法はさまざまで、柔らかい刺激から比較的しっかりした刺激まで幅があります。対象となる年齢はおおよそ10歳前後まで。小学校入学前(6歳頃)までは刺入することはほとんどなく、症状が長引いた場合にのみ大人と同じように刺入を行うことがあります。
私たちのグループでは、この技術をベトナムに移植しました。現地で定着するかどうか、今後の動きが気になるところです。日本国内では小児はりの会も活発化し、ドイツやアメリカの鍼灸師にも認知され、技術が伝わり始めています。
かつての指圧がそうであったように、小児はりもまた海外で広まり、そして残っていく可能性が高いのではないかと感じています。

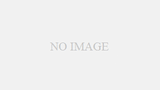

コメント