チェルノブイリ事故から長い年月が過ぎました。
けれども放射能汚染は「終わった話」ではなく、数百年、あるいは数千年単位で私たちに影響を与え続けます。セシウム137やストロンチウム90は数百年、プルトニウム239に至っては数万年も残存するというのですから、人間の時間感覚ではほとんど「永遠」に近いものです。
日本のお茶も汚染されていた
先日、古い新聞記事を読み返して驚きました。
1987年8月24日付の朝日新聞(三重版) によれば、三重県度会町の茶生産グループがチェルノブイリ事故後に採れた茶を放射能汚染のため出荷停止にしていたとのこと。
生活クラブ生協が国の基準の10分の1という自主基準を設けており、そこを超えたために、7~8トンの茶葉を廃棄。被害額は2000~2500万円にも上ったと報じられていました。
当時の私は日本のお茶まで汚染されていたことを知りませんでした。フランスやイタリア、ポーランドでの汚染の話は記憶にありましたが、改めて「放射能は国境を越えて広がる」現実を思い知らされます。
原子力発電の「正体」
京都大学原子炉実験所の小出裕章先生のレポートを読むと、原子力発電とは「要するに水を沸かしてタービンを回す装置」であることが分かります。
しかもウランを掘り、濃縮し、プルトニウムを取り出すまでに膨大なエネルギーを消費し、二酸化炭素も放出します。つまり「原子力=クリーンエネルギー」というイメージは神話にすぎないのです。
現在も続く不安
これは決して過去の話ではありません。
-
原発攻撃の危険性
-
福島第一原発事故の処理水をめぐる国際的な対立
-
中国や韓国の原発排水問題
原子力発電はエネルギー問題だけではなく、国際安全保障や外交問題にまでつながっているのです。
改めて考えます。
「原子力発電とは一体何なのか」。
便利な電気の裏側に、世代を越えて背負わなければならないリスクが潜んでいることを忘れてはいけないと思います。


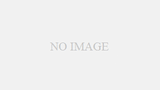
コメント